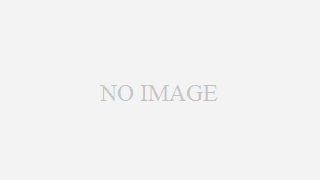飛鳥時代(593年〜710年)は、聖徳太子の改革から大化の改新・壬申の乱を経て、藤原京を造営し奈良時代へ移行するまでの、日本の国家体制が大きく変革した時期です。大陸からの仏教・先進文化の導入や、豪族・皇族間の政争、律令体制の整備などを通じて、後の奈良時代・平安時代の基盤が築かれました。
【飛鳥時代(593年~710年)】
└────────────────────────────────────
├─◆ Episode 1:「飛鳥の夜明け――大陸文化との出会い」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 6世紀末ごろ(仏教伝来期)~推古天皇即位前まで
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 仏教伝来と百済などとの関係
│ │ ├─ 大陸(中国・朝鮮半島)からの文化・技術流入
│ │ └─ 大和朝廷(大王)の成立背景と飛鳥への遷都
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 飛鳥の地をめぐる豪族や朝廷が、外来文化(仏教)を受容・対立しながら新しい政治・社会の形を模索するドラマ
│
├─◆ Episode 2:「聖徳太子と推古天皇――国家の礎を築く」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 推古天皇即位(593年)~聖徳太子の死(622年)前後
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 聖徳太子(厩戸皇子)の政治改革(冠位十二階・憲法十七条など)
│ │ ├─ 仏教・儒教を取り入れた官僚制整備
│ │ └─ 遣隋使による対外関係と先進文化の受容
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 推古天皇のもとで摂政となった聖徳太子が新しい国づくりを推進し、豪族中心から中央集権的な官制へ移行しようとする物語
│
├─◆ Episode 3:「蘇我氏の台頭――豪族社会の変化」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 推古朝~皇極天皇期(7世紀中頃)
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 聖徳太子没後の政治変動
│ │ ├─ 蘇我氏による仏教保護と権力集中
│ │ └─ 他豪族(物部氏など)との対立構造
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 蘇我馬子から蝦夷・入鹿へと続く権力継承と豪族間の対立が激化する中、乙巳の変(645年)へとつながる政治緊張を描く
│
├─◆ Episode 4:「大化の改新――新しい国づくりへの挑戦」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 645年 乙巳の変~孝徳天皇の治世(大化・白雉年間)
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 蘇我氏滅亡後の政変と公地公民制などの政治改革
│ │ ├─ 中大兄皇子(天智天皇)・中臣鎌足(藤原鎌足)の役割
│ │ └─ 難波宮への遷都と地方行政の再編
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 乙巳の変を機に、中央集権化を目指す大規模改革が始まる。理想と現実のはざまで揺れながらも、律令制へと繋がる基盤づくりを進める物語
│
├─◆ Episode 5:「壬申の乱――王権をめぐる激動」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 672年、天智天皇崩御直後~天武天皇即位
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 天智天皇の後継者争い(大友皇子 vs. 大海人皇子)
│ │ ├─ 壬申の乱の勃発と国家規模の内戦
│ │ └─ 天武天皇による王権強化と統治システム再構築
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 天智天皇死後、後継をめぐる激しい内戦が勃発。大海人皇子が勝利し、天武天皇として即位、王権強化へ向けた新たな体制が整備されていく過程を描く
│
└─◆ Episode 6:「新しい都と文化――藤原京から奈良時代へ」
├【時代・範囲】
│ └─ 天武・持統朝(7世紀後半)~平城京遷都(710年)
├【主なポイント】
│ ├─ 藤原京の造営と条坊制による都市計画
│ ├─ 律令体制の整備(天武・持統天皇の政策)
│ └─ 奈良時代(平城京)への移行
└【あらすじ要旨】
└─ 壬申の乱後、天武・持統両天皇が中央集権をさらに推進し、藤原京を造営。次第に奈良の地へ遷都が検討され、710年の平城京遷都で飛鳥時代が幕を下ろす