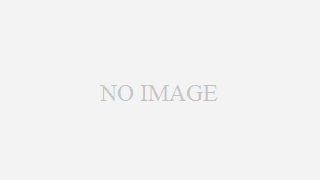江戸時代(1603~1868年)は、徳川家康による幕府創設を起点に幕藩体制が確立され、参勤交代や鎖国などを通じて約260年にわたり国内を安定統治した時代です。
元禄・化政と呼ばれる華やかな町人文化が開花する一方、財政難から度重なる幕政改革が行われ、19世紀には黒船来航をきっかけに幕末の混乱が深まりました。
最終的に尊王攘夷運動や倒幕運動が加速し、大政奉還によって徳川幕府は終焉を迎え、明治維新へと移行していきます。
【江戸時代(1603年~1868年)】
└──────────────────────────────────────────
├─◆ Episode 1:「江戸幕府の成立」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 戦国末期~江戸幕府初期(1600年 関ヶ原~1605年頃)
│ ├【テーマ・学習ポイント】
│ │ ├─ 徳川家康の台頭と関ヶ原の戦いの意義
│ │ ├─ 江戸幕府開府の経緯と豊臣家との緊張
│ │ └─ 新政権発足による社会変化(中央から江戸へ拠点移動)
│ ├【あらすじ要旨】
│ │ └─ 家康が戦国の混乱を制し、征夷大将軍となり江戸幕府を創設。
│ │ 豊臣秀頼との関係や諸大名の配置を背景に、新たな時代の幕が上がる。
│ └【主要人物・関連事項】
│ ├─ 徳川家康・豊臣秀頼・石田三成
│ ├─ 関ヶ原の戦い
│ └─ 江戸幕府初期の支配体制
│
├─◆ Episode 2:「幕藩体制の確立と社会構造」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 江戸初期~17世紀中期(家光治世~1650年前後)
│ ├【テーマ・学習ポイント】
│ │ ├─ 武家諸法度・参勤交代など幕藩体制のしくみ
│ │ ├─ 士農工商・身分制度と年貢制度
│ │ └─ 江戸・大阪・京都など都市と農村の発展
│ ├【あらすじ要旨】
│ │ └─ 家光期に大名統制が強化され、支配体制が安定。
│ │ 社会階層の区分がはっきりし、町人・農民がそれぞれの生活基盤を築く。
│ └【主要人物・関連事項】
│ ├─ 徳川家光
│ ├─ 保科正之(幕政の補佐)
│ └─ 参勤交代・武家諸法度・年貢制度・三都(江戸・大阪・京都)
│
├─◆ Episode 3:「鎖国体制と外交」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 17世紀前半~18世紀前半(島原の乱~鎖国体制の維持期)
│ ├【テーマ・学習ポイント】
│ │ ├─ キリスト教禁教と島原の乱
│ │ ├─ 鎖国政策(長崎出島、対馬など)と貿易の限定
│ │ └─ 朝鮮通信使、琉球王国、蘭学への影響
│ ├【あらすじ要旨】
│ │ └─ 島原の乱以降、幕府はキリスト教を弾圧し国際関係を制限。
│ │ 出島を通じてオランダ・清との貿易を継続しつつ、
│ │ 周辺国との外交を続けながらも、鎖国体制が長く続く。
│ └【主要人物・関連事項】
│ ├─ 松平信綱(島原の乱の鎮圧)
│ ├─ オランダ商館長・朝鮮通信使
│ └─ 出島、隠れキリシタン、蘭学
│
├─◆ Episode 4:「元禄文化の花開き」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 17世紀後半~18世紀初頭(元禄期:1688~1704年)
│ ├【テーマ・学習ポイント】
│ │ ├─ 元禄文化の特徴(町人文化・上方中心)
│ │ ├─ 井原西鶴・松尾芭蕉・近松門左衛門などの文芸
│ │ └─ 経済発展と庶民の娯楽
│ ├【あらすじ要旨】
│ │ └─ 綱吉期の政策が賛否を呼ぶ中、上方の商人や町人が
│ │ 歌舞伎・人形浄瑠璃・俳諧など多彩な文化を創出。
│ │ 庶民が主役となる新しい芸術が台頭する。
│ └【主要人物・関連事項】
│ ├─ 徳川綱吉
│ ├─ 井原西鶴・松尾芭蕉・近松門左衛門
│ └─ 歌舞伎・人形浄瑠璃・浮世草子
│
├─◆ Episode 5:「享保・寛政の改革と幕政の転換」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 18世紀前半~後半(徳川吉宗の享保の改革~松平定信の寛政の改革)
│ ├【テーマ・学習ポイント】
│ │ ├─ 幕府財政の悪化と政治改革(目安箱、上米の制など)
│ │ ├─ 百姓・町人への影響と民衆の反応
│ │ └─ 改革の成果と限界
│ ├【あらすじ要旨】
│ │ └─ 吉宗が年貢増徴や目安箱など新政策を試み、一時的に安定化を図るが
│ │ 後の松平定信の改革では倹約令など厳しい方針が民衆の不満を招く。
│ └【主要人物・関連事項】
│ ├─ 徳川吉宗(8代将軍)
│ ├─ 松平定信(老中)
│ └─ 目安箱、享保の改革、寛政の改革
│
├─◆ Episode 6:「化政文化と庶民の暮らし」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 18世紀末~19世紀前半(文化・文政・天保期)
│ ├【テーマ・学習ポイント】
│ │ ├─ 江戸を中心とする町人文化(浮世絵、黄表紙、洒落本など)
│ │ ├─ 寺子屋教育と庶民の識字率向上
│ │ └─ 都市経済の発展と農村との格差
│ ├【あらすじ要旨】
│ │ └─ 江戸で人気を集める娯楽・出版・風俗画が大流行。
│ │ 葛飾北斎や歌川広重らが浮世絵を発展させ、庶民生活に彩りを添える。
│ └【主要人物・関連事項】
│ ├─ 葛飾北斎・歌川広重(浮世絵師)
│ ├─ 十返舎一九・式亭三馬(滑稽本・洒落本)
│ └─ 寺子屋教育、瓦版、江戸の町人文化
│
├─◆ Episode 7:「天保の改革と幕末の危機」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 19世紀前半~中葉(天保の改革:1841~1843年)
│ ├【テーマ・学習ポイント】
│ │ ├─ 幕府財政の深刻化と水野忠邦の改革
│ │ ├─ 株仲間解散・上知令など大胆な施策
│ │ └─ 百姓一揆・打ちこわしの増加と社会不安
│ ├【あらすじ要旨】
│ │ └─ 商人や農民に重い負担を強いた改革が反発を招き失敗、
│ │ 幕府の権威は動揺。海外の脅威も迫る中、幕末への不安が拡大する。
│ └【主要人物・関連事項】
│ ├─ 水野忠邦(老中)
│ ├─ 株仲間、商人・農民
│ └─ 天保の改革、百姓一揆・打ちこわし
│
└─◆ Episode 8:「黒船来航と幕府の終焉」
├【時代・範囲】
│ └─ 19世紀中葉~1867年(ペリー来航~大政奉還)
├【テーマ・学習ポイント】
│ ├─ ペリー来航と開国、不平等条約の締結
│ ├─ 尊王攘夷・倒幕運動の激化
│ └─ 徳川幕府の崩壊と明治維新への道
├【あらすじ要旨】
│ └─ 黒船来航で鎖国体制が崩壊。条約により国内混乱が広がり、
│ 薩長などの倒幕運動が加速。最終的に大政奉還で幕府は滅び、
│ 新時代(明治維新)へ移行する。
└【主要人物・関連事項】
├─ ペリー、井伊直弼(安政の大獄)
├─ 徳川慶喜(最後の将軍)
└─ 坂本龍馬、桂小五郎、西郷隆盛などの志士