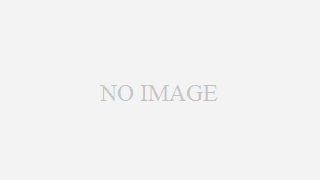江戸時代に生まれた蔦屋重三郎が、華やかな町人文化と幕府の取り締まりのはざまで新しい出版を切り拓く。
やがて、その志は弟子や周囲の人々に受け継がれ、明治維新を経ても文化の灯を絶やさずに伝えられていく。
現代では、大手書店チェーン「TSUTAYA」が重三郎の名を受け継ぎ、人々の求める“面白さ”を届ける拠点となっている。
┌──────────────────────┐
│【Episode 1】
│ 「江戸中期の町人文化と若き蔦屋重三郎の志」
│
│ ├─ シーン1:にぎわう江戸下町
│ ├─ 江戸の人口増加と出版文化の勃興
│ └─ 幼い重三郎が本に魅せられる
│
│ ├─ シーン2:奉公先の書店にて
│ ├─ 書店の仕事を学び、版元の仕組みに触れる
│ └─ 厳しい指導と興味の芽生え
│
│ └─ シーン3:夢に向かって――独立を決意する
│ ├─ 奉公の修行を経て得た自信
│ └─ 新しい時代を作るための第一歩
└──────────────────────┘
┌──────────────────────┐
│【Episode 2】
│ 「吉原と芝居小屋が紡ぐ物語――蔦屋重三郎の出版革命」
│
│ ├─ シーン1:新たな版元・蔦屋の店先にて
│ ├─ 独立した重三郎の店に客が増え始める
│ └─ 吉原や芝居の噂がもたらす刺激
│
│ ├─ シーン2:吉原見物――遊郭文化との出会い
│ ├─ 遊女や客、仲介人との交流で新たな発想
│ └─ 華やかさと哀しみが混在する世界
│
│ └─ シーン3:芝居小屋と新しい本づくり
│ ├─ 歌舞伎役者・絵師との協業
│ └─ 画期的な洒落本・浮世絵企画への挑戦
└──────────────────────┘
┌──────────────────────┐
│【Episode 3】
│ 「幕府の目と町人の知恵――蔦屋重三郎が挑んだ出版統制」
│
│ ├─ シーン1:急な召喚――幕府からの通達
│ ├─ 松平定信による寛政の改革と取り締まり
│ └─ 蔦屋重三郎、奉行所に呼び出される
│
│ ├─ シーン2:作家・絵師との苦悩
│ ├─ 山東京伝・喜多川歌麿らの処罰と葛藤
│ └─ 規制下での創作意欲をどう保つか
│
│ └─ シーン3:決意と小さな光
│ ├─ 規制をかいくぐる書き方・表現の工夫
│ └─ 蔦屋の情熱が再び燃え上がる
└──────────────────────┘
┌──────────────────────┐
│【Episode 4】
│ 「町人文化を照らす灯――蔦屋重三郎の晩年とその遺産」
│
│ ├─ シーン1:長引く統制と新しい発想
│ ├─ 幕府の取り締まりが続き、苦境に立つ蔦屋
│ └─ それでも新たな企画を模索
│
│ ├─ シーン2:未来を担う者たちとの交流
│ ├─ 若手版元・弟子との意見交換
│ └─ 山東京伝・喜多川歌麿らとの連携
│
│ └─ シーン3:蔦屋重三郎、最後の大仕事と旅立ち
│ ├─ 病に倒れ、周囲に店を託す
│ └─ 江戸文化を支える理念の継承
└──────────────────────┘
┌──────────────────────┐
│【Episode 5】
│ 「受け継がれる志――蔦屋重三郎が灯した江戸文化の未来」
│
│ ├─ シーン1:惜しまれる蔦屋重三郎の死と店の混乱
│ ├─ 嘆き悲しむ人々
│ └─ 幕府の監視が続く不安
│
│ ├─ シーン2:次世代の台頭と新たな挑戦
│ ├─ 弟子や若手版元が中心となり復興を模索
│ └─ 山東京伝・歌麿と協力し、規制をかわす企画
│
│ └─ シーン3:江戸から未来へ――文化の灯は消えず
│ ├─ 人々の娯楽を求める心の強さ
│ └─ 後の時代(明治維新)へ続く出版文化
└──────────────────────┘
┌──────────────────────┐
│【Episode 6】
│ 「時を超える蔦の想い――蔦屋重三郎から現代TSUTAYAへ」
│
│ ├─ シーン1:幕末から明治へ――名前だけが残った“蔦屋”
│ ├─ 動乱の時代に語り継がれる重三郎の名
│ └─ 明治・大正・昭和と変化する社会
│
│ ├─ シーン2:現代・大手書店チェーン“TSUTAYA”の誕生秘話
│ ├─ 蔦屋重三郎への憧れからブランド名を採用
│ └─ 「文化のコンビニ」という理念
│
│ └─ シーン3:未来を創る“文化のコンビニ”――TSUTAYAが受け継ぐもの
│ ├─ 多様なメディアとカフェ併設で新しい“場”を提供
│ └─ 江戸時代の“町人文化を届ける”精神との共通点
└──────────────────────┘