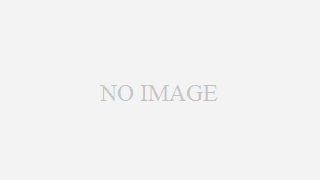鎌倉時代(1185頃~1333年)は、日本で初めて武士が政治の主導権を握った時代です。
源平合戦の勝利後、源頼朝が鎌倉に幕府を開き、守護・地頭を全国に置くことで武家政権を確立しました。頼朝の死後は北条氏が執権として実権を握り、承久の乱で朝廷を抑え、武家法である御成敗式目を制定して統治の基盤を固めます。
一方、元寇(蒙古襲来)に対する防衛や度重なる戦費負担により、御家人の不満が高まり、財政も疲弊。
最終的に後醍醐天皇の倒幕運動により1333年に鎌倉幕府は滅亡し、時代は建武の新政へと移行していきました。
鎌倉時代 (1185~1333)
└─【Episode 1】源平の戦乱と新しい時代の幕開け
│ ├─ 源平合戦と朝廷・武士の対立
│ ├─ 源頼朝・源義経・平清盛など主要人物
│ └─ 武家政権が誕生する転換点
└─【Episode 2】鎌倉幕府の誕生と御家人たちの結束
│ ├─ 守護・地頭の設置
│ ├─ 御恩と奉公の関係
│ └─ 鎌倉幕府の制度と政治手腕
└─【Episode 3】執権政治の確立と承久の乱
│ ├─ 北条政子・北条義時らによる実権掌握
│ ├─ 承久の乱で朝廷(後鳥羽上皇)と衝突
│ └─ 御成敗式目(武家法)による統治の確立
└─【Episode 4】元寇(蒙古襲来)と日本を守った“神風”の真相
│ ├─ 文永の役(1274)・弘安の役(1281)
│ ├─ 防塁建設や御家人への負担
│ └─ “神風”の由来と幕府財政の困窮
└─【Episode 5】武士と民衆を支えた新仏教と芸術のはなし
│ ├─ 浄土宗・浄土真宗・日蓮宗・禅宗の広がり
│ ├─ 武士・民衆への宗教的影響
│ └─ 運慶・快慶らによる芸術作品
└─【Episode 6】幕府の終焉と新しい時代の予感
├─ 元寇後の恩賞問題と財政難
├─ 得宗専制への御家人の不満
├─ 後醍醐天皇らの倒幕運動
└─ 幕府滅亡と建武の新政への序章