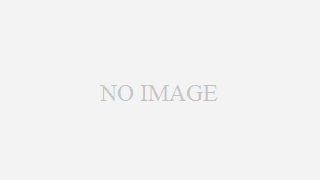鎌倉幕府滅亡(1333年)後、後醍醐天皇が理想の政治(建武の新政)を試みるも武士の不満を招き、南北朝の対立が生まれました。
やがて足利尊氏が室町幕府を開き、三代将軍・足利義満のもとで南北朝は合一し、華やかな北山文化が栄えます。
しかし八代将軍・足利義政の代には応仁の乱(1467年)が起こり、室町幕府の統制力が大きく揺らぎ、戦国時代へと突入しました。
【南北朝・室町時代(1333年~1467年頃)】
└───────────────────────────────────────────
├─◆ Episode 1:鎌倉幕府崩壊と建武の新政
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 1330年前後~1336年頃(建武の新政)
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 鎌倉幕府の衰退と倒幕運動(後醍醐天皇、足利尊氏、新田義貞)
│ │ ├─ 建武の新政(後醍醐天皇の理想政治)と武士の不満
│ │ └─ 朝廷 vs. 武家政権の対立の始まり
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 後醍醐天皇が幕府打倒に成功し、新政を行うが武士層の反発を招き、やがて尊氏との対立が深まる
│
├─◆ Episode 2:南北朝のはじまり ~ 後醍醐天皇と足利尊氏
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 1336年~1337年頃(南北朝の成立期)
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 京都朝廷(北朝) vs. 吉野朝廷(南朝)の二重国家
│ │ ├─ 足利尊氏の動向と光明天皇擁立
│ │ └─ 楠木正成ら南朝派武将の奮戦と、戦乱の全国拡大
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 尊氏が京都に別の天皇を立て、後醍醐天皇は吉野へ下る。日本は南朝・北朝に分裂し、長期戦乱へ突入する
│
├─◆ Episode 3:室町幕府の成立と初期体制
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 1338年(尊氏が征夷大将軍就任)~14世紀後半
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 室町幕府の組織(将軍・管領・守護大名)
│ │ ├─ 幕府内部の権力争い(足利尊氏 vs. 高師直・足利直義など)
│ │ └─ 全国統治における守護大名の強大化
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 尊氏が室町幕府を開くが、中央・地方の統治は困難を極める。幕府内部の対立も続き、南北朝の戦乱はまだ収束しない
│
├─◆ Episode 4:足利義満と南北朝の合一 ~ 北山文化の黄金期
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 14世紀後半~1392年(南北朝合一)+ 義満の治世
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 足利義満の政治手腕と幕府の全盛期
│ │ ├─ 南北朝合一(1392年)による国内統一
│ │ └─ 北山文化(金閣寺、能楽など)の隆盛
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 義満が権力を一手に集約し、ついに南北朝を合一。金閣寺を象徴とする華麗な文化が花開き、室町幕府は権威の頂点を迎える
│
├─◆ Episode 5:次世代将軍と東山文化 ~ 足利義政の時代
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 15世紀中頃~1460年代前半(義政の治世)
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 足利義政と東山文化(銀閣、書院造、茶の湯、わび・さび)
│ │ ├─ 幕府の政治力低下と守護大名間の対立激化
│ │ └─ 芸術・美意識の発展とその背景
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 義政が政治を顧みず文化に傾倒する一方、幕府内外の対立が深まり、応仁の乱への火種が芽生える
│
└─◆ Episode 6:応仁の乱と戦国時代への扉
├【時代・範囲】
│ └─ 1467年 応仁の乱勃発 ~ 乱の余波(戦国時代の幕開け)
├【主なポイント】
│ ├─ 将軍継嗣問題や有力大名の対立(東軍 vs. 西軍)
│ ├─ 京都市中の大規模破壊と長期戦乱
│ └─ 室町幕府の権威失墜と“下剋上”の風潮
└【あらすじ要旨】
└─ 義政の後継争いに端を発し、守護大名同士の内紛が京都を焼き尽くす大乱に発展。幕府が統制力を失い、全国は戦国時代へ突入する