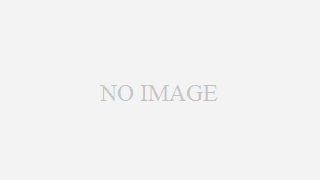奈良時代(710〜784年ごろ)は、平城京を中心に律令制度が整えられ、聖武天皇の大仏造立や光明皇后の福祉事業、遣唐使を通じた国際交流などで政治・文化が大きく発展した時代です。『古事記』『日本書紀』の編纂による国家アイデンティティの確立や、天平文化の隆盛が特徴的でしたが、政争や天災を経て都は長岡京・平安京へ移り、奈良時代は幕を閉じました。
【奈良時代(710年~784年ごろ)】
└────────────────────────────────────
├─◆ Episode 1:「平城京誕生~律令国家の整備と新都建設」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 710年の平城京遷都前後~奈良時代初期の制度整備
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 元明天皇による平城京遷都
│ │ ├─ 律令国家の仕組み(班田収授法・戸籍整備など)
│ │ └─ 中央集権体制の形成と地方格差の拡大
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 都建設に携わる官人や民衆の視点を通して、唐をモデルにした都市づくりと律令制度の運用を描く
│
├─◆ Episode 2:「聖武天皇と大仏~国家事業としての仏教」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 聖武天皇(在位724~749年)の仏教政策と大仏建立期
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 国家事業としての東大寺大仏(盧舎那仏)建立
│ │ ├─ 仏教で国を守る(鎮護国家)の思想
│ │ └─ 行基ら僧侶の活躍と民衆救済
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 疫病や天変地異に苦しむ国を救うため、聖武天皇が大規模仏教事業を推進するドラマ
│
├─◆ Episode 3:「光明皇后と福祉のはじまり~施薬院・悲田院の物語」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 8世紀中頃、光明皇后(聖武天皇の皇后)が主導した福祉政策
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 施薬院(医療・薬の提供)と悲田院(貧困者救済)
│ │ ├─ 仏教的慈悲心と社会福祉のつながり
│ │ └─ 奈良時代の貧富の差・庶民の生活実態
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 疫病流行や飢えに苦しむ人々を救うため、光明皇后が施薬院・悲田院を創設する人間ドラマ
│
├─◆ Episode 4:「日本書紀と古事記~日本のルーツを記す営み」
│ ├【時代・範囲】
│ │ ├─ 『古事記』編纂(712年)
│ │ └─ 『日本書紀』編纂(720年)の前後
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 国家による正史編纂事業の政治的背景
│ │ ├─ 神話・伝承と史実をどうまとめたか
│ │ └─ 日本という国のアイデンティティ形成
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 舎人親王らが中心となり、各地の伝承や氏族の記録を収集しながら“公式の歴史”を編纂する奮闘と葛藤
│
├─◆ Episode 5:「天平文化の花ひらき~正倉院宝物と遣唐使」
│ ├【時代・範囲】
│ │ └─ 8世紀前半~中頃、天平文化最盛期
│ ├【主なポイント】
│ │ ├─ 遣唐使による唐との交流と国際的影響
│ │ ├─ 正倉院宝物に見る工芸・美術の高度化
│ │ └─ シルクロードを通じた東西文化の融合
│ └【あらすじ要旨】
│ └─ 遣唐使や留学生が持ち帰った最新の技術・文化が宮廷で花開き、正倉院に収められた宝物が後世への遺産となる過程
│
└─◆ Episode 6:「奈良の終焉~都の動揺と平安への架け橋」
├【時代・範囲】
│ └─ 8世紀後半(称徳天皇・道鏡の政争)~桓武天皇の長岡京・平安京遷都
├【主なポイント】
│ ├─ 政争や僧の政治介入(道鏡)による朝廷の混乱
│ ├─ 疫病・天災の頻発と財政難
│ └─ 平城京から長岡京・平安京へ都が移る経緯
└【あらすじ要旨】
└─ 称徳天皇(孝謙天皇)と道鏡の政治騒動を背景に朝廷が都を変える決断へ至り、奈良時代が幕を閉じる